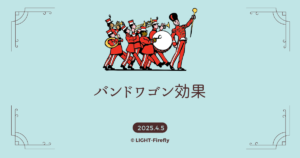この記事の読了目安時間は約 3 分です
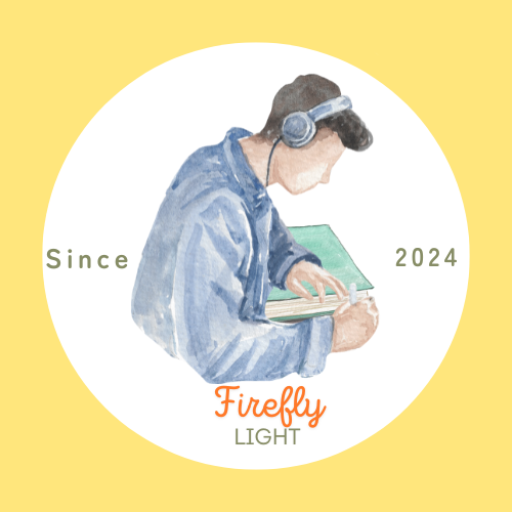
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
「サンクコスト効果」という言葉を聞いたことはありますか?行動経済学を学んだことがある人であれば、一度は耳にしたことがあるかもしれません。この効果は、既に支払ったお金や費やした時間といった「回収できないコスト」に引きずられ、合理的な判断ができなくなる心理的な現象を指します。
本記事では、サンクコスト効果の基本的な定義や具体例を解説し、ビジネスに役立てる方法やサンクコスト効果に引きづられない考え方についても考察します。自分自身の判断や行動を見直すきっかけにしてみてください。
用語解説:行動経済学
出典:共同通信社 共同通信ニュース用語解説
サンクコスト効果とは?

サンクコスト効果とは、既に費やしたお金や時間などの「回収できないコスト」に囚われてしまい、合理的な判断ができなくなる現象です。たとえば、映画のチケットを購入したものの、内容がつまらないと感じた場合でも、「お金を払ったから最後まで観なければ」と考えるのがその典型例です。
サンクコスト効果の本質は、「過去のコストが未来の選択に不合理な影響を与える」という点にあります。合理的には、今後の利益や満足度を基準に判断すべきですが、過去の損失を取り戻そうとする心理がそれを妨げてしまいます。
サンクコスト効果の語源
サンクコスト効果と消費者心理

サンクコスト効果は、われわれ消費者心理に大きな影響を与えます。たとえば、以下のような状況を思い浮かべてください。
- 高額な食べ放題
お金を多く払った分、元を取ろうと考えて無理にでも食べ過ぎてしまい、結果的に満足感が低下する。 - クレーンゲーム
何度も挑戦して投資額が増えると、「ここで諦めたら損してしまう」という心理が働き、景品を取ろうとさらにお金をつぎ込んで結果的に投資額(損失)が増える。 - 趣味に合わない本を最後まで読む
趣味に合わない本であっても一度読み始めると「最後まで読まなければこれまで費やした時間無駄になる」と感じて最後まで読んでしまう。 - 見放題のサブスクリプションサービス
月額料金を支払っているからといって、興味のない番組や映画を無理して視聴する。
これらの例からわかるように、サンクコスト効果は消費者の行動に不合理な選択をもたらすことが多いのです。また、私達の身の回りには沢山のサンクコスト効果を利用した仕掛けがあり、誰もがこの心理的な罠にはまる可能性があることがわかります。
ビジネスにサンクコスト効果を取り入れるポイント
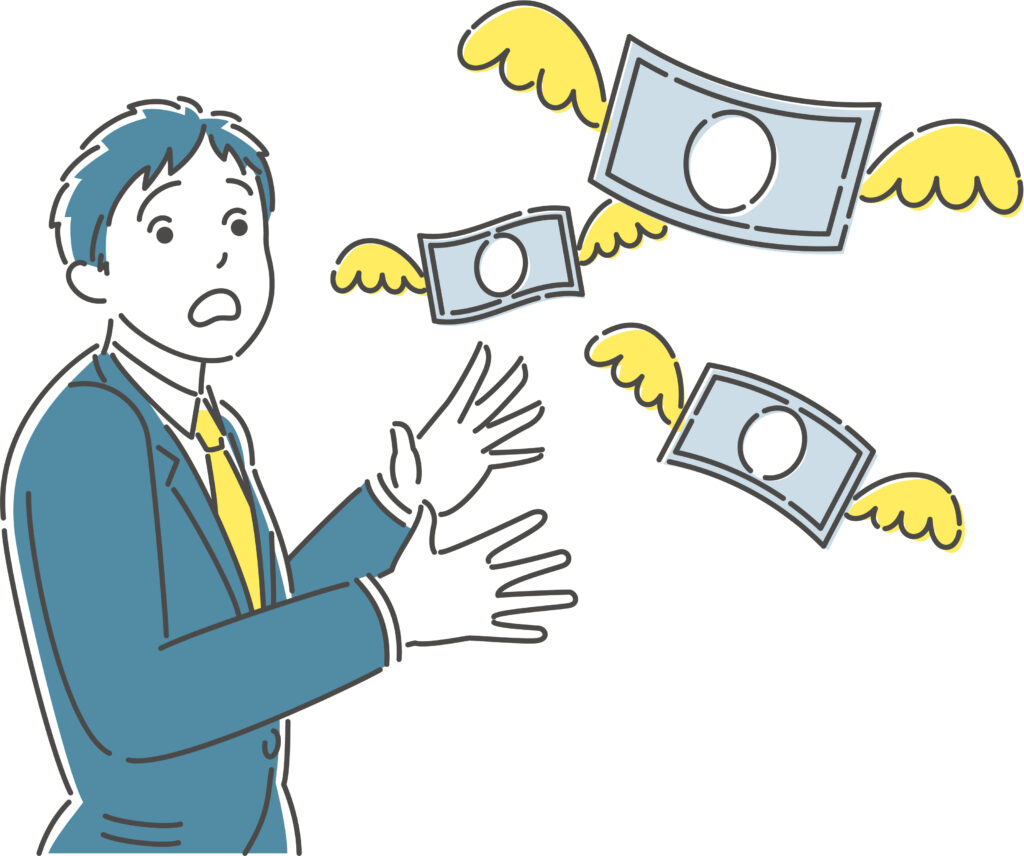
ビジネスにおいて、サービスの提供者はサンクコスト効果をうまく活用することで、消費者の購買意欲を高めたり、場合によってはサービスの満足度を向上させることが可能です。以下は具体的な活用ポイントです。
定期的な支払いが発生するサブスクリプションモデルを採用することで消費者のサービス利用を促進し、その後の消費者の満足度を維持/向上させることで顧客離れを防ぐことができる。
初回ディスカウントを提供して消費者の初期費用を下げるなど、初回投資に着目したオファーを用意することで初回投資した消費者の「損をしたくない」という心理を刺激し、リピーターへと繋げる。
ポイント制度や会員特典を設けることで、これまでの「サンクコスト」を消費者に意識させ消費者の継続的な購入意欲を維持する。
サンクコスト効果に引きずられないために

- 選択肢を明確化する
他の選択肢を紙に書き出して比較すると、より冷静に判断できます。 - 埋没コストを認識する
「回収できないコストはすでに終わったもの」と正しく理解し、決断に影響を与えないよう心がけます。 - 目標に基づいた選択をする
自分の最終的な目的や目標に立ち返り、目標に適した合理的な行動を選びましょう。 - 過去ではなく未来を基準に判断する
「これから得られる利益や満足度」に焦点を当て、過去の費用や努力と未来に対する選択を切り離して考える習慣をつけましょう。
これらを実践することで、サンクコストにとらわれず、より合理的で満足度の高い決断ができるようになります。


まとめ
サンクコスト効果は、私たちの日常やビジネスに深く関係している心理的現象です。この効果を理解することで、自分の行動を冷静に見直し、合理的な判断を行う力を身につけることができます。また、自分がサービスの提供者となるビジネスの場面では、消費者心理を意識したサービス設計やプロモーションに役立てることが可能です。本記事をきっかけに、日常生活や仕事でサンクコスト効果に気づき、それを活用または克服する方法を考えてみてください。
行動経済学を学ぶのにおすすめの書籍
\今すぐチェックしてみる/