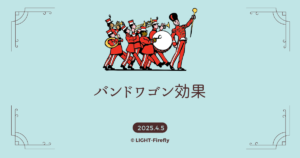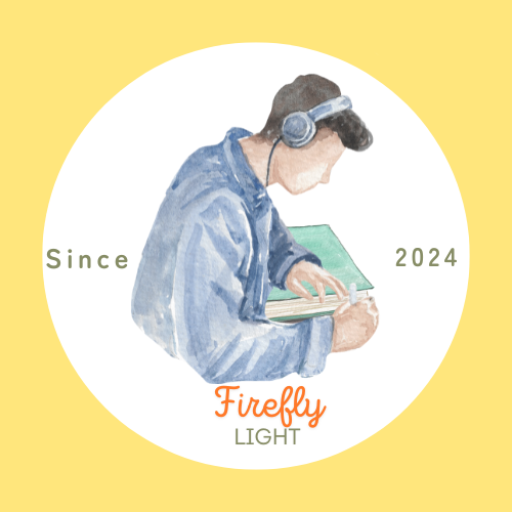
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
株価や経済のニュースを見ていると、「PBRが1倍を割った」「PERが高水準」などといった言葉をよく目にします。しかし、普段のビジネスシーンではあまり使う機会がないため、聞き流しているサラリーマンの方も多いのではないでしょうか。
とはいえ、企業で働く以上、「自分や周りの会社が市場でどう評価されているのか」を知ることは、仕事への意識や行動にも影響します。 また、転職先や取引先を評価する際にも、株価指標の知識は役立ちます。
 ライト
ライト本記事では、株価指標の中でも基本でありながら実用性が高い「PBR」と「PER」について解説します。数字に苦手意識がある方でも分かりやすくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
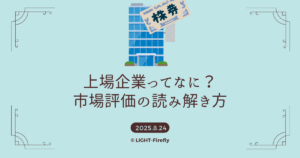
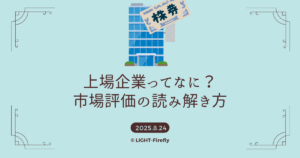
株価指標で企業の何が分かる?
株価や株式指標も意識する癖をつけよう


日々の業務では目の前の数字や成果に追われがちですが、一歩引いて「会社が市場でどう見られているか」に目を向けることは、サラリーマンにとっても大切な視点です。
株価は日々変動するため一喜一憂する必要はありませんが、「株価指標」はもう少し本質的な企業の価値や成長性、将来への期待度を示すヒントになります。
たとえば、同じような株価の企業が2社があっても、市場での評価(割安であるか否か)は異なる場合があります。その違いを読み解くヒントになるのがPERやPBRといった指標なのです。
PERとPBRについて
PERとは


PER(Price Earnings Ratio)=株価 ÷ 1株あたり利益(EPS)
PERは、企業の「利益」に対して、株価が何倍に評価されているかを示す指標です。より平たく言えば、「今の利益水準が続けば、何年で投資額を回収できるか」を表しているとも言えます。
たとえば、PERが15倍なら「15年で元が取れる」という見方ができます。PERが高ければ将来の成長が期待されており、低ければ現時点では割安と評価されているとも解釈されます。ただし、PERの高さだけで企業の「良し・悪し」は判断できません。将来の成長余地や業界の特性なども加味する必要があります。
PERの数値は利益の大小に大きく影響を受けるため、年度によって大きく変動することがあります。また、企業が赤字であった場合にはそもそもPERを算出できません。PERは株価が割安かどうか検討するのを助ける有効な指標ですが、時間軸を長めにとってPERの推移を確認するなど慎重な取り扱いも求められます。
ここでの1株あたりの利益というのは、配当ではありません。1株あたりの利益に配当性向をかけたものが「配当」になります。
PBRとは
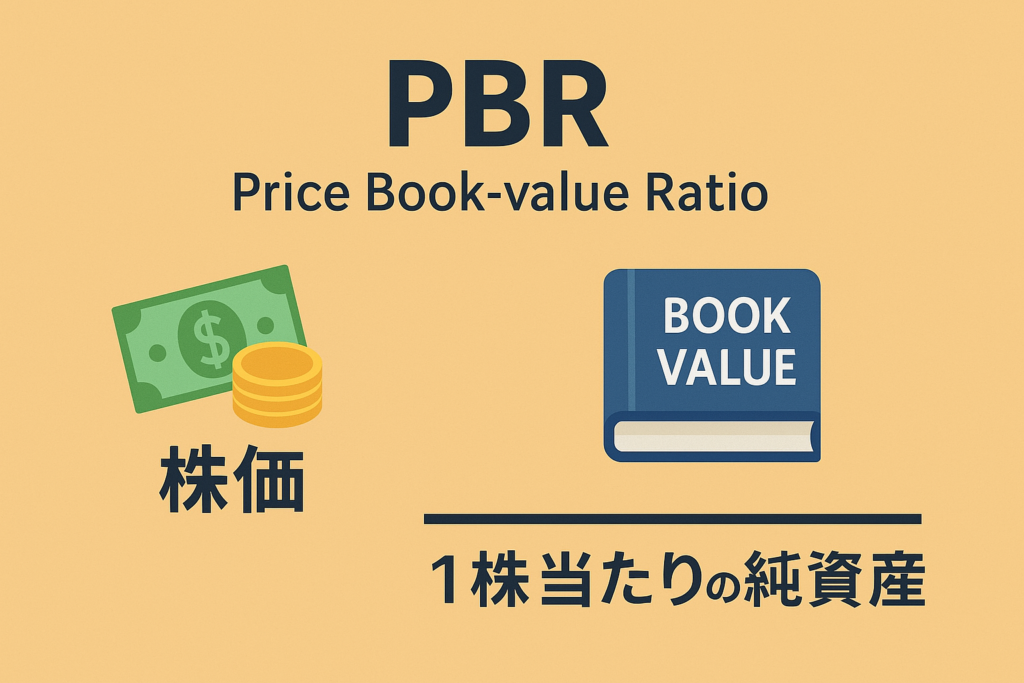
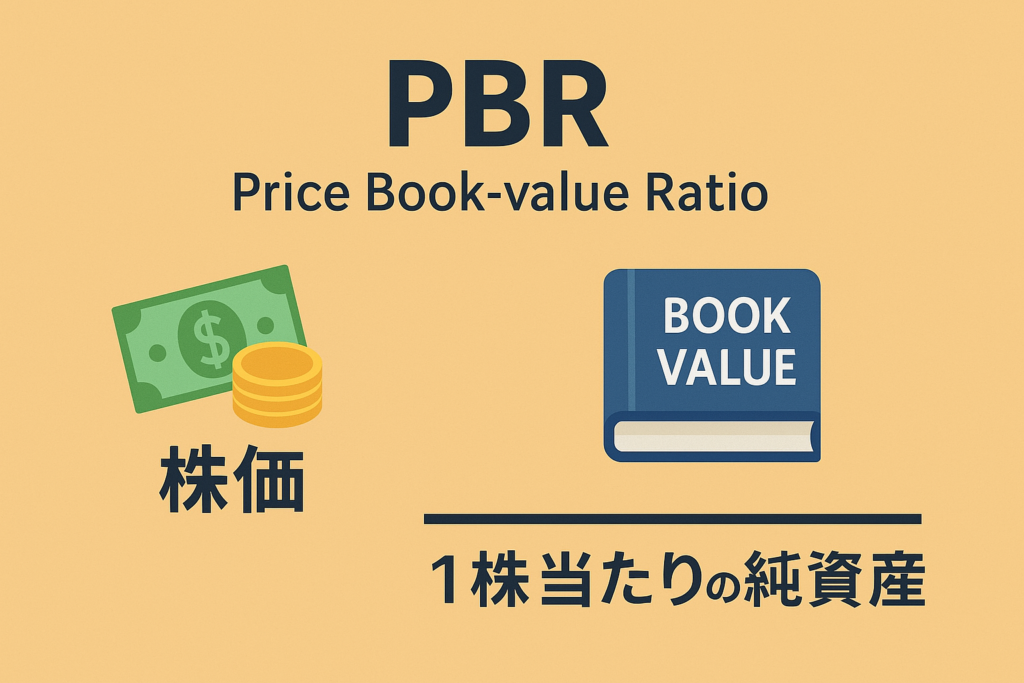
PBR(Price Book-value Ratio)=株価 ÷ 1株あたり純資産(BPS)
PBRは、企業の「純資産」に対して株価がどのくらいの倍率になっているかを示す指標です。純資産とは、会社が持っている資産から借金などの負債を引いた「正味の価値」とも言えます。
たとえば、PBRが1倍なら、株価は企業の純資産と同じ水準。1倍を下回ると「会社をまるごと買って資産を処分したほうが得では?」と考えられる可能性もあります。
つまり、PBRは企業の「解散価値」や「資産の割安さ」を測るモノサシです。
PER/PBRそれぞれの目安となる指標
PERの参考目安
PERは、15倍が一般的な目安とされます。これは「企業が利益を出し続ければ15年で元が取れる」水準と考えられているからです。
ただし、PERもPBRと同様に業界によって大きく異なるため、単純に数字だけで判断するのは危険です。
たとえば、ITやバイオといった成長期待が高い業種はPERが30倍以上になることもあります。一方、成熟したインフラ系企業などは10倍以下のこともあります。
したがって、PERは「その業界の中で高いのか低いのか」という相対評価が重要です。
| 業種 | PERの参考目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| IT・テック系 | 20〜30倍以上 | 将来への成長期待が高く、PERは高め |
| 小売・サービス | 15〜25倍 | 安定成長なため、やや高めの評価がつく |
| 製造業 | 10〜20倍 | 業種によって大きくバラつきあり |
| 金融・インフラ | 8〜15倍 | 成熟業種のためPERは低めに算出される |
PBRの参考目安
PBRは、1倍が一つの大きな目安とされています。なぜなら、「純資産=会社の本来の価値」であり、それより株価が下回っていると、市場から過小評価されていると考えられるからです。
実際、日本取引所グループ(JPX)は、PBRが1倍未満の企業に対して改善を促す方針を示しており、経営陣も指標を意識せざるを得ない状況になっています。
ただし、資産型の企業(不動産業など)はPBRが低くなりやすく、IT企業などは軽い資産構成でも高評価される傾向があります。そのため、業種ごとにPBRの「適正水準」は異なります。
| 業種 | PBRの目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 銀行・保険 | 0.3~0.7倍 | 純資産が大きく、PBRが低く出やすい傾向 |
| 製造業(重工業) | 0.8~1.2倍 | 設備投資が多く資産が大きいためやや低め |
| 製造業(軽工業) | 1.0~2.0倍 | 成長性が高い業種ではPBRも高くなる傾向 |
| 小売・外食 | 1.5~3.0倍 | ブランド力や収益性が評価されやすい |
| IT・テクノロジー | 2.0~5.0倍 | 成長期待が高く、資産より利益重視で評価 |
| 不動産 | 0.5~1.2倍 | 保有資産によるブレが大きい |
| 電力・ガス | 0.7~1.1倍 | 安定業種だが成長性が低くPBRは抑えめ |
まとめ
PERやPBRといった株価指標は、一見すると専門的で難しそうに見えますが、「株価に対する企業の利益/資産のウェイト」測る指標です。PERやPBRを意識してニュースや株価に目を向けることで、以下のような視点を得ることができます。
- 企業が保有する資産に対して、株価はどう評価されているのか(PBR)
- 企業の利益に対して、株価は割安か割高か(PER)
- 市場はその企業に将来どのくらい期待しているのか
- 自分が働いている会社や、転職候補先企業は「市場や投資家からどう見られているか」
仕事に直接関係ないように思えるかもしれませんが、経済や企業活動を俯瞰する力は、将来的にキャリアの武器になるはずです。ぜひ、ニュースや四季報を読むときに「この企業のPBRやPERはどのくらいだろう?」と気にする癖をつけてみてください。少しずつ数字の意味がわかってくると、企業を見る目も変わってくるはずです。