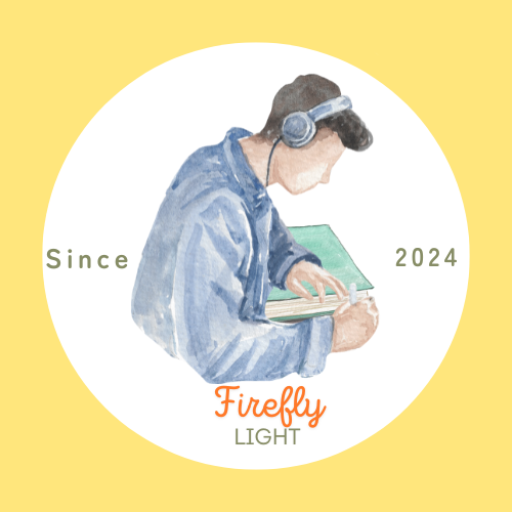
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
この記事の読了目安時間は約 2 分です
行動経済学では、人は「得」より「損」を大きく感じるとされています。これは「損失回避」という心理で説明され、日常における私たちの消費行動に大きな影響を与えています。本記事では、損失回避の仕組みとビジネスでの活用法について紹介します。
用語解説:行動経済学
出典:共同通信社 共同通信ニュース用語解説
損失回避とは?

私たち人は「1万円得た時の嬉しさ」と「1万円を落とした時の悲しさ」、どちらの感情の方がが強く印象に残るでしょうか。
きっと多くの人が、「失った時の悲しさの方がずっと大きい」と感じるはずです。これは錯覚ではなく、れっきとした人間の心理傾向です。この傾向は、行動経済学の世界では「損失回避(Loss Aversion)」と呼ばれています。研究によれば、人は同じ額の「得」と「損」を比較したとき、損の方を2倍以上大きく感じる傾向があるとも言われています。
「ネガティビティバイアス」という心理学用語でも、人はポジティブな情報よりネガティブな情報の影響をより強く受けると説明しています。

損失回避を利用したビジネス戦略

損失回避は人間の心理的な傾向になりますが、ビジネスの現場では、この心理的傾向を巧みに利用したビジネス戦略が数多く存在します。
期間限定やタイムセール
「今だけ」「限定50個」「本日まで」というコピーは、「今買わないと損をする」という消費者の気持ちを引き起こすことで、購買意欲を高めています。
無料トライアルの後に有料化
サブスクリプションサービスなどの一定期間無料でサービスを使わせたあとに自動課金する仕組みは、一度得た快適さを「失いたくない」という損失回避の感情をうまく利用したビジネス戦略です。
「返金保証」や「返品無料」
返金保証や返品制度を用意することで、消費者は「損する可能性が小さい」と判断し、安心して購入に踏み切ることができます。
損失回避の知識で衝動買いも抑えられる

「損したくない!」という気持ちが先走ってしまい、必要のないものをついつい買って後悔してしまう人も多いのではないでしょうか。ここで活用したいのが、自分の中の「損失回避スイッチ」に気づくことです。
衝動買いしそうになったときには、次のように自問してみましょう。
- 「今買わなければ本当に損するのか?」
- 「その“損”は一時的な気持ちだけではないか?」
- 「本当に必要な買い物なのか?」
人は「得」より「損」を大きく感じる生き物であるという理解の上で、一歩引いて“冷静な損得”を見極める習慣をつけることで、無駄な出費を抑えることができます。

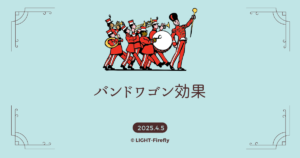

まとめ
人間は「得をしたい」という思いよりも、「損をしたくない」という感情に強く引っ張られます。これが、行動経済学で言う「損失回避」です。この心理は、私たちのビジネス判断や日常生活、さらにはキャリアの選択にまで影響を与えています。損失回避の仕組みを知れば、無意識の購買行動や判断ミスを防ぐヒントにもなります。そして逆に、仕事の中でこの心理を上手に活用できれば、より説得力のある提案や営業活動も可能になるでしょう。








