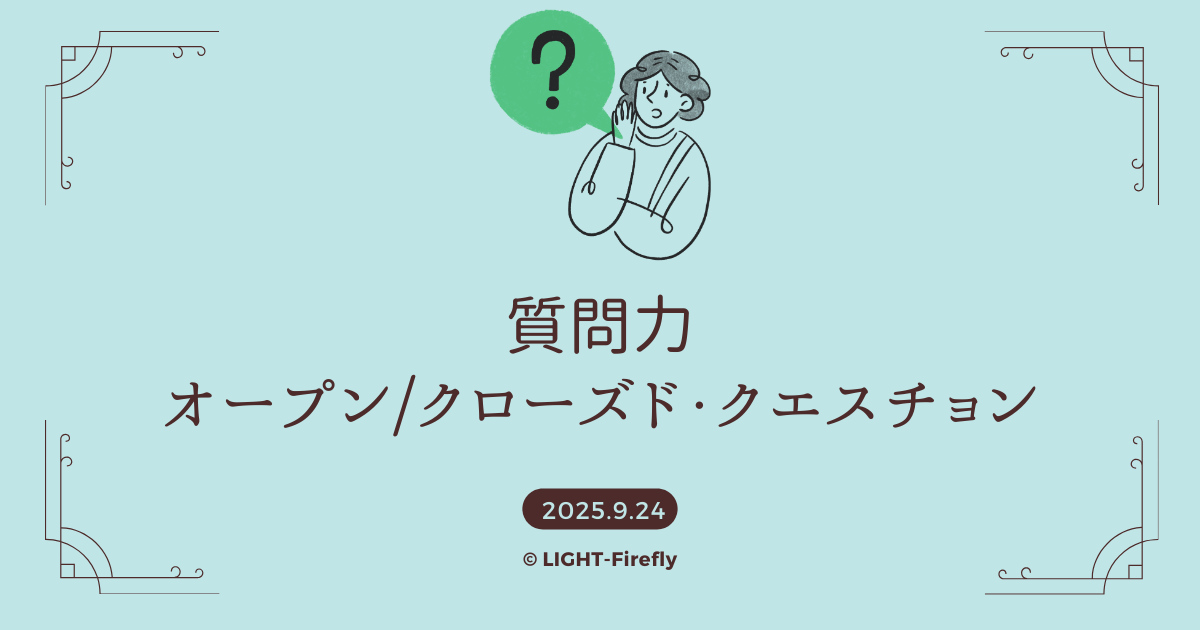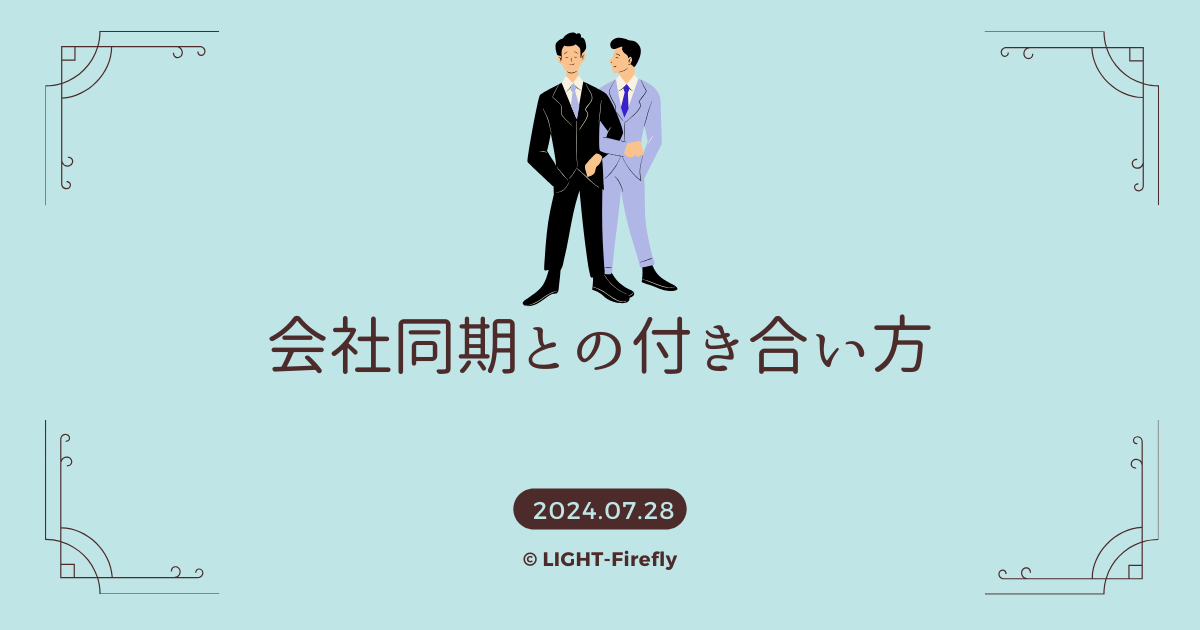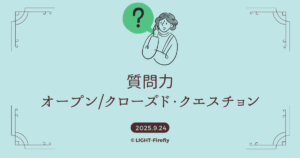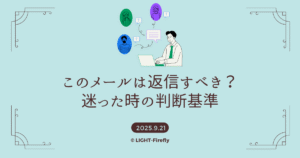この記事の読了目安時間は約 3 分です
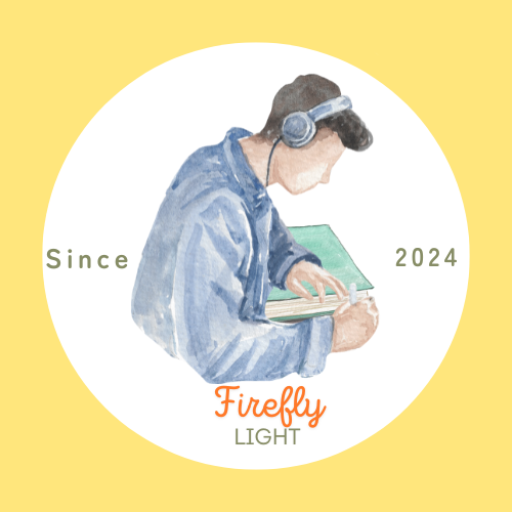
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
あなたは「質問したら期待していた回答が返ってこなかった」なんてこと、ありませんか?ビジネスシーンでは、同じ「質問」でも聞き方ひとつで得られる情報や相手の反応がガラリと変わります。ちょっとした言い回しの差で会議や商談が有意義になったり、逆に時間だけが消費されたりすることもあります。
 ライト
ライト本記事では質問の仕方としてよく使われるオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの考え方や違い、現場での使い分けテクニックをわかりやすく紹介します。
まず覚えておきたい2種類の質問
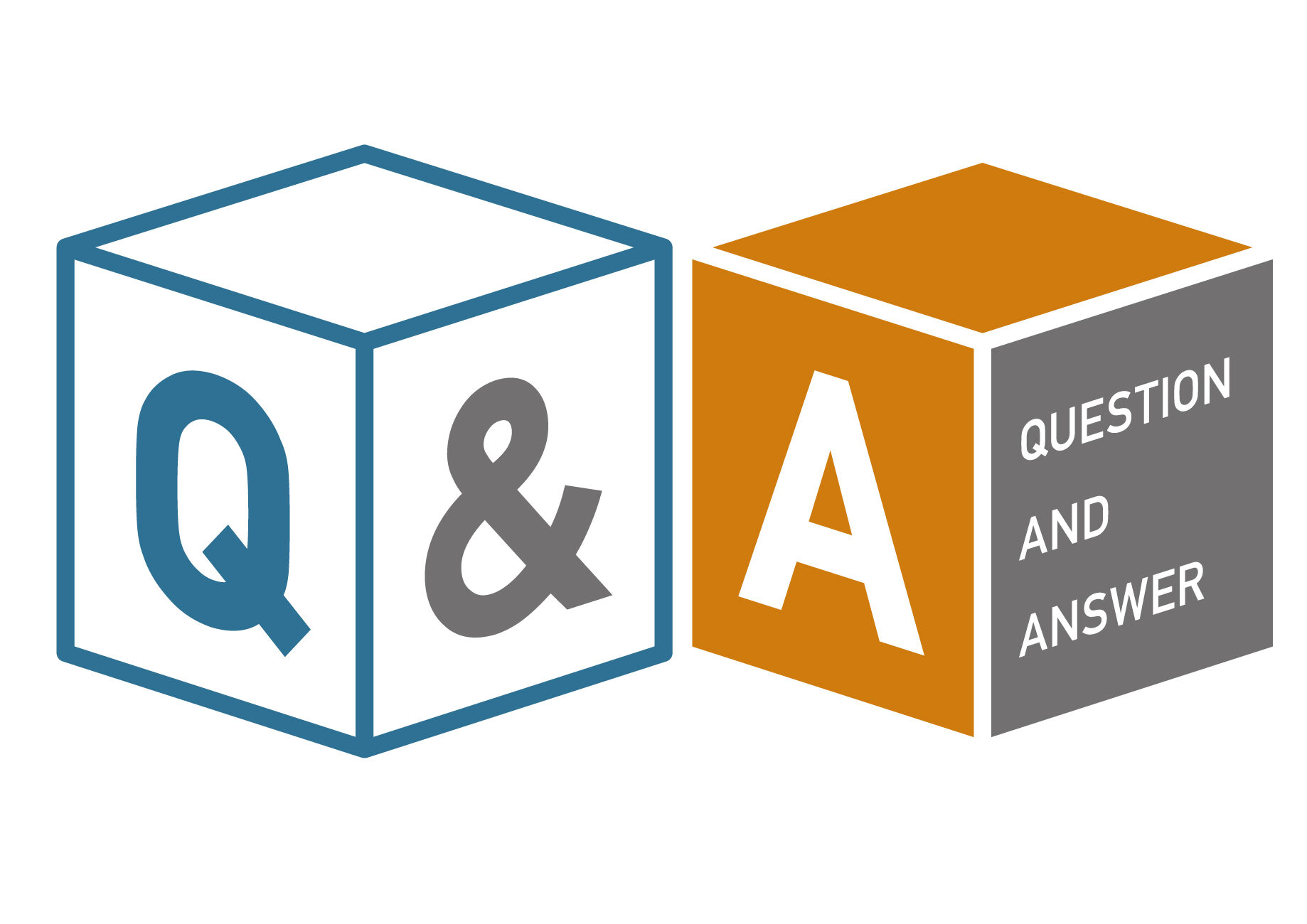
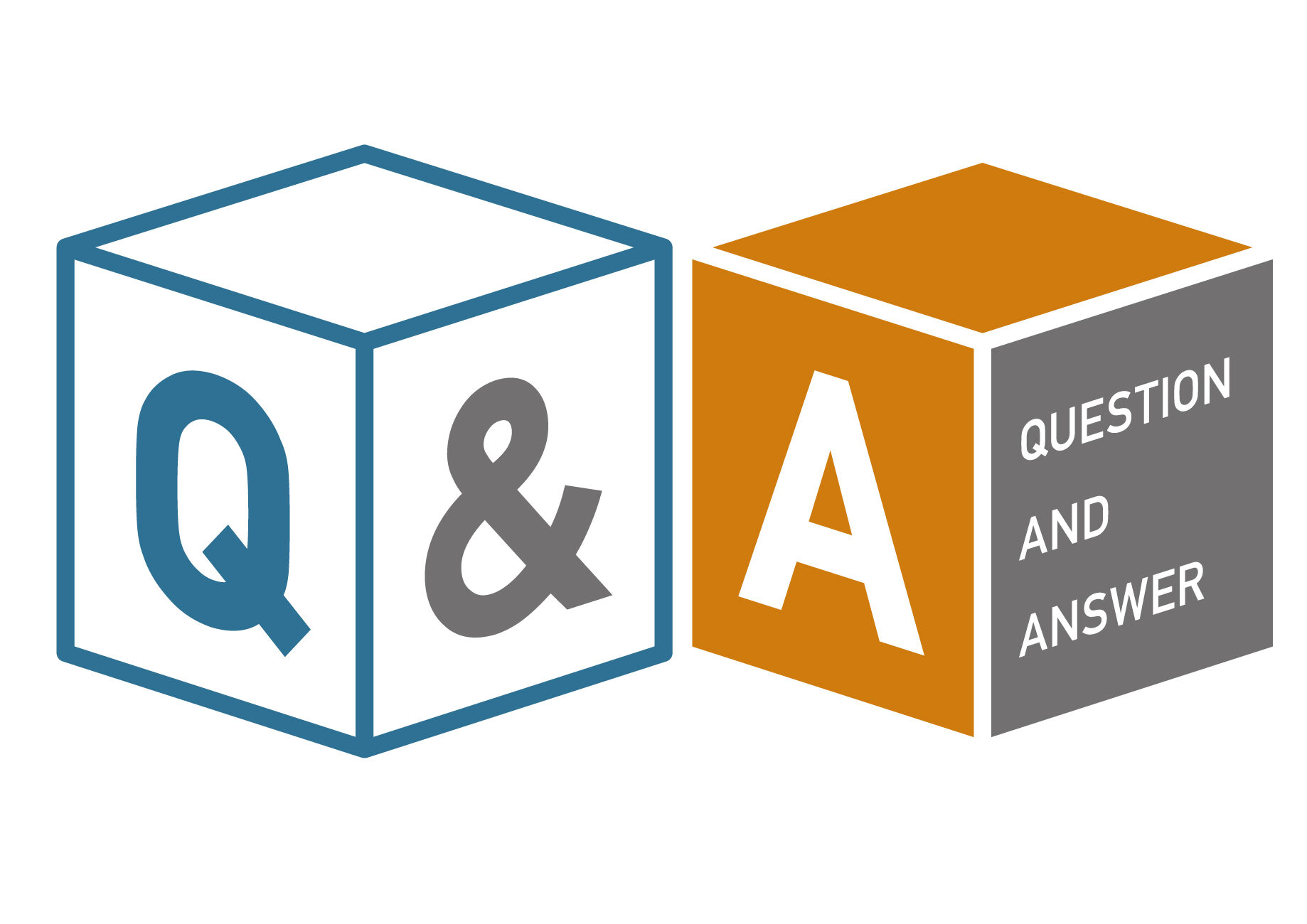
私たちが質問をする際には、まず相手からどんな情報や回答を得たいのかをイメージすることが大切です。本音やアイデアを引き出したいのか、それともこれまでの話し合いから導かれる回答を確認をしたいのか。期待する回答の種類によって適切な質問の仕方は変わります。
ビジネスシーンでよく用いられるのがオープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの考え方です。前者は相手に自由に答えてもらうことで会話を広げ、本音やアイデアを引き出すのに役立ちます。後者は「はい/いいえ」や限られた選択肢の中から答えてもらうことで、効率的に結論を導いたり議論を進めたりするのに有効です。
状況に応じてこの二つを上手に使い分けることで、コミュニケーションの質が高まり、無駄なく必要な情報を得られるようになります。
オープンクエスチョンは自由度の高い回答を導く
定義:はい/いいえで答えられない、相手が自由に説明できる質問。相手の考え・感情・背景を引き出すのに向いている。
オープンクエスチョンの例
- 「御社が弊社のサービスに期待していることはなんですか?」
- 「セミナー運営を通して、今回の反省点や今後の改善点は何がありますか?」
クローズドクエスチョンは解像度の高い回答を導く
定義:はい/いいえ、または選択肢の中から答える質問。相手の意志確認や合意形成に向いている。
クローズドクエスチョンの例
- 「この資料は明日までに提出すれば大丈夫ですか?」(はい/いいえ)
- 「A案で進めますか?それともB案にしますか?」(選択肢)
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンの使い分け


- 情報を引き出したい → オープン
-
意見や原因、背景を聞きたいときはまずオープンで広げる。ブレストなどにはオープンクエスチョンを用いる。
- 確認・承認・次のアクションを決めたい → クローズド
-
結論/役割/期限を決めるときはクローズドで選択肢を締めることにより業務が進められる。参加者が多い会議はクローズドクエスチョンを意識することで会議の方向性を舵取りできる。
| 種類 | 特徴 | 適した場面 | 例 |
|---|---|---|---|
| オープンクエスチョン | 自由に答えられる相手の考えを引き出せる | 意見収集、原因分析、アイデア出し | 「このプロジェクトで問題点は何ですか?」 |
| クローズドクエスチョン | はい/いいえ、選択肢で答えられる/結論を絞りやすい | 事実確認、意思決定、合意形成 | 「この資料は明日までに必要ですか?」 |
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンは基本的にセットで使うのが鉄則です。「このプロジェクトの問題点は?」(オープン) →「その問題点をどうやって解決しますか?」(オープン) →「誰がいつまでに解決しますか?」(クローズド)のようにオープンからクローズドへ質問を移行させることで、解決策をいくつか検討してから結論を出すことができます。
オープンクエスチョンとクローズドクエスチョンを意識した商談の流れ
商談の冒頭(状況や課題を知る)
- 「まず、弊社にお声がけいただいた背景を教えていただけませんか?」(オープン)
- 「〇〇について御社の抱えている課題を教えていただけませんか?」(オープン)
商談の途中(課題の深掘り)
- 「それは関係者にどのような影響がありますか?」(オープン)
- 「重要度は高・中・低でいうとどれですか?」(クローズド)
- 「いつまでにその課題を解決したいと考えていますか?」(クローズド)
商談の終盤(合意形成)
- 「では、このようなご提案はいかがですか?」(クローズド)
- 「来週中に改めてお返事いただけるということでよろしいですか?」(クローズド)



議論の終盤においては、検討の温度感を測るためにテストクロージングを入れることも有効です。


つい忘れがちな質問の仕方で気をつけたいポイント


- 質問が曖昧
「増税についてあなたはどう考えますか?」などのような抽象度の高い質問は、相手に思考の負担を強いることになり、期待する答えが返ってきづらい。 - 期日や数字が曖昧
「早めに」ではなく「◯日までに」、「5件くらい」ではなく「5件」と期限や数字はできるだけ明確にして確認しないと合意形成後にトラブルが発生する可能性がある。 - 二つの質問を同時する(ダブルバレル)
「この案で進めていいですか?〇〇さんには情報共有が必要ですか?」などのように複数の質問をまとめてしない。一問一答のコミュニケーションを意識しないと、回答が疎かになってしまう。


まとめ
オープンは「情報収集」、クローズドは「確認と決定」。用途を切り分けて使えば会話の生産性が劇的に上がります。会議や商談では「まずオープンで本音を引き出す → 最後にクローズドで合意を取る」を意識してみましょう。小さな実践を積み重ねて大きな質問力を育んでいきましょう。