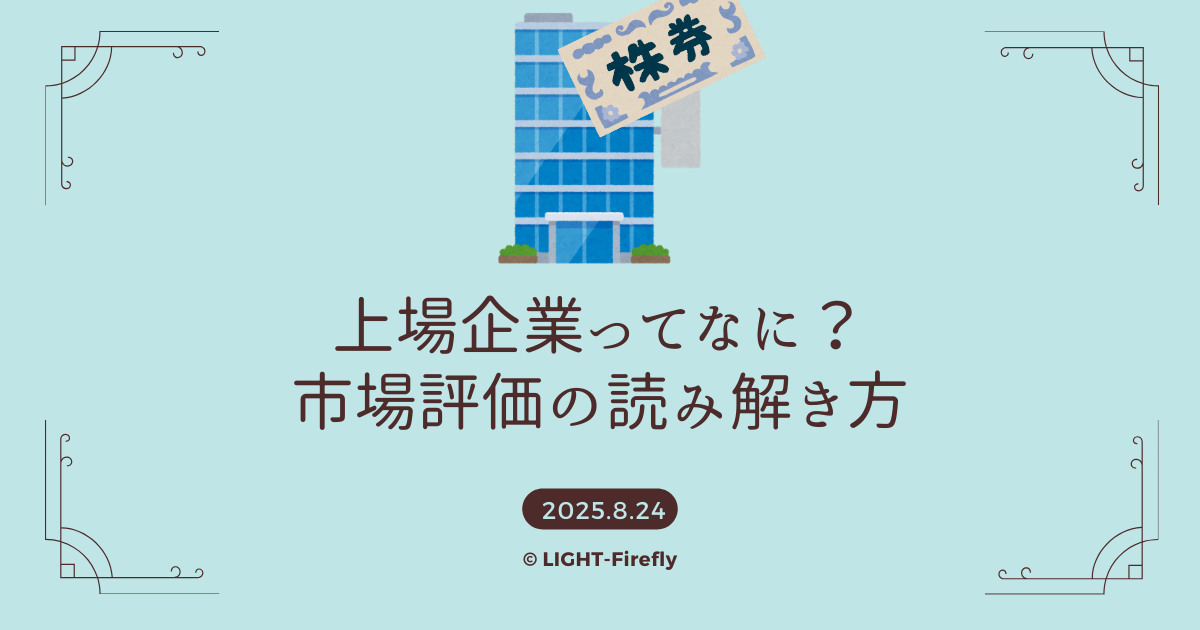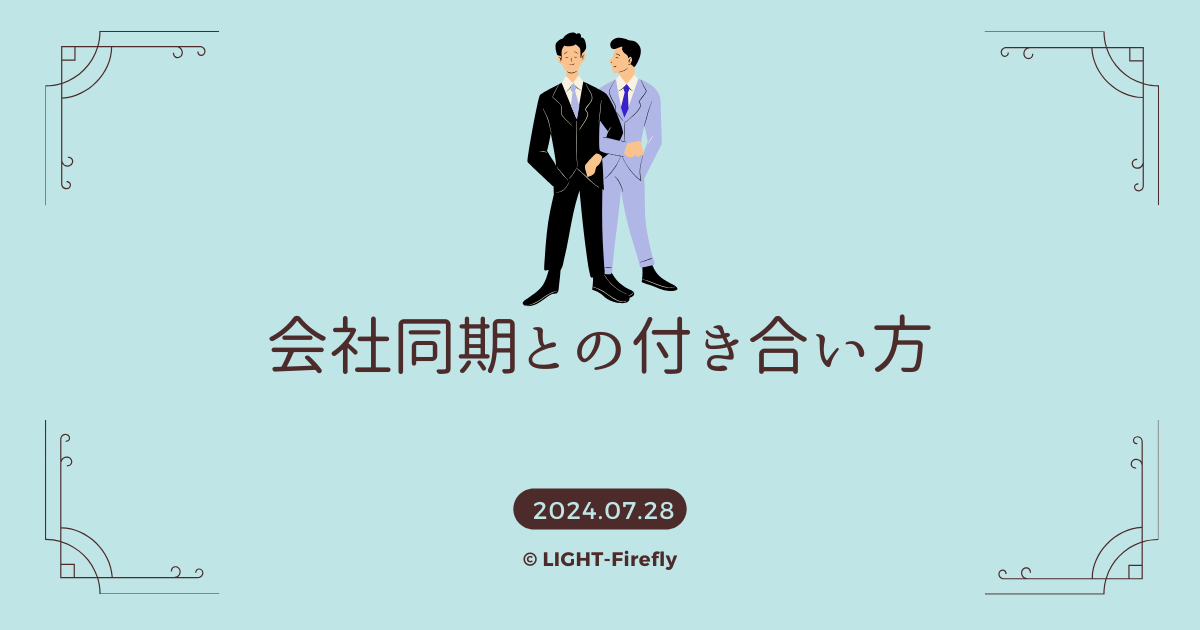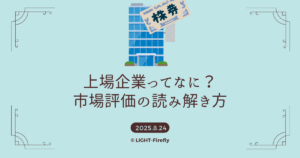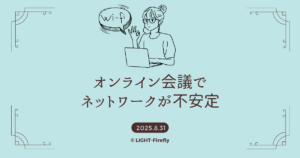この記事の読了目安時間は約 3 分です
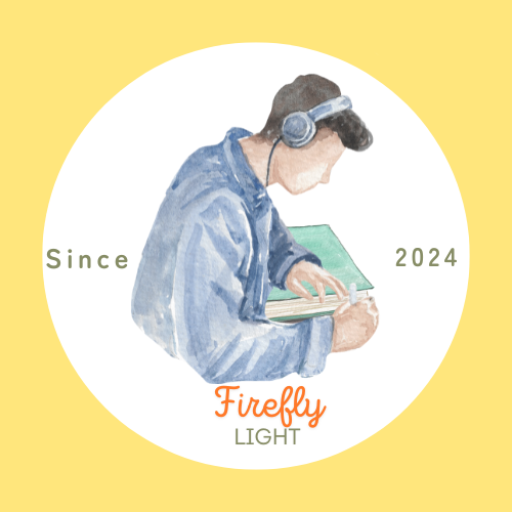
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
- 上場企業=株式を証券取引所で一般投資家が売買できる企業
- 東証の市場はプライム/スタンダード/グロースの3つの種類がある
- 時価総額は「株価 × 発行済株式数」で計算され、市場がその会社をいくらと見ているかの目安に
- PER・PBR・PSRなどの指標を組み合わせて評価をある程度読み解くことも可能
- IR(Investor Relations)は投資家向け情報。社員にとっても“自社を理解する教科書”に
 ライト
ライト「うちの会社は上場企業らしいけど、上場企業がどんなものかあまり分かっていない」そんな2〜30代のビジネスパーソンもいるのではないでしょうか。こちらの記事では上場企業とは?に始まり、株価と市場評価の関係をシンプルに解説します。ネットで見かける「バリュー株」「グロース株」「PER」「PBR」といった用語を見て迷子になった人でも大丈夫。この記事を読み終えるころには、会社の“市場評価”がある程度つかめるようになります。
上場企業ってどういうこと?


上場企業とは一言でいうと「自社の株式を証券取引所に公開している企業」です。株式が証券取引所に公開されると、一般の投資家が自由に株を売買できます。会社は上場することにより「資金調達の手段が増える」「社会的な信頼を得れる」というメリットを得ます。その一方で、株主への情報公開義務が生じ経営の透明性(情報開示)などに対する責任も求められるようになります。
上場のメリット
上場のデメリット



大企業=上場というイメージがあったけど、NTTドコモやサントリーは上場していないのね。同社の株を買いたいと思ったのに残念・・・
東証の3つの市場区分と特徴(プライム、スタンダード、グロース)


東京証券取引所(東証)の市場は現在、プライム/スタンダード/グロースの3区分です。企業の規模や成長段階、投資家層へのアピールの違いによって分かれています。下記の表でそれぞれの特徴を比較してみましょう。
| 市場区分 | 特徴 | 代表的な上場企業 |
|---|---|---|
| プライム市場 | ・大規模でグローバルに投資家を惹きつける企業が中心 ・高いガバナンス基準、情報開示を求められる ・流動性や時価総額の基準が最も厳しい | トヨタ自動車、ソニーグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ |
| スタンダード市場 | ・国内投資家を主な対象とした安定的な企業が中心 ・プライムほどではないが一定のガバナンス/情報開示が必要 ・中堅規模の企業が多い | サイゼリヤ、山崎製パン、オリエンタルランド |
| グロース市場 | ・新興企業や成長期待の高い企業が中心 ・安定収益よりも成長性を重視 ・赤字企業やPERが極端に高い企業も多い | ジモティー、プログリット、ispace |
時価総額は現在の企業価値と考える


時価総額とは投資家が市場でその企業に付けた「仮想的な値札」です。時価総額は下記計算式で求められ、株式市場で得ている評価をもとに会社規模をある程度推し量ることができます。
この時価総額には売上や従業員数といった実態の規模だけでなく、将来の成長や収益力への期待が織り込まれます。
- 同じ売上規模でも、収益性や将来の成長期待が高い企業ほど時価総額は大きくなりやすい
- プライム市場に上場している安定収益企業は「信頼」によって時価総額が大きくなりやすい
- グロース市場に上場している新興企業は「期待」が大きいと時価総額が先行しやすい



時価総額が株価に基づいて計算されるってことは、株価が毎日変動するように時価総額も毎日変動するのね。
株価指標で市場の評価を読み解く(PER・PBR・PSR)


株価が割高か割安かを一発で計算する魔法の数式はありません。ただし、複数の指標を組み合わせて企業の実力や市場から得ている評価をある程度読み解くことは可能です。今回は基礎編として3つだけ押さえましょう。
PER(株価収益率)
意味: 現在の株価が利益の何年分に当たるか。ざっくり15倍前後が平均的な目安と言われます。
たとえば、一株1,500円の株が、1株当たり100円の利益を生み出したと仮定します。この場合、上記PERの計算式にあてはめるとPERが15倍です。この株を15年間握りしめて利益を毎年100円生み出し続ければ、元本分の1,500円を回収できる計算になります。
誤解が生じないように補足するとPERは「株価が利益の何年分か」を測る指標で、あくまで利益ベースの理論的な年数になります。実際に株主の手元に返ってくるお金をベースに回収スピードを測るには、配当利回りや株主還元策を見る必要があります。
トヨタなどのプライム市場に上場する企業のPERは15倍に近い水準で推移することが多く、一方でグロース市場に上場する企業はPERを計算すると15倍を大きく超える企業も多く散見されます。PERが高くても「これから 1株当たり利益(EPS)が大きく伸びる」という将来期待を買う投資家が一定数おり、高PERの企業は成長の期待が株価にプレミアムとして乗っているような状況です。事実、GMOリサーチ&AIは記事執筆時点では直近でPERが1,000倍を超える水準になっており、15倍という平均値はあくまでも目安として理解した方がいいと思います。



私の感覚では、プライム/スタンダード市場に上場していてPER15倍未満は今後の業績急成長に対する期待は低め、15‐50倍付近は期待高め。グロース市場ではPER15‐50倍付近は普通で51倍以上は少し高いかなとう印象です。
PBR(株価純資産倍率)
意味: 会社が保有する純資産(資産−負債)と比べて株価が高いか低いか。1倍が一つの目安で、1倍未満は「解散価値より安い」状態と表現されることも。
PBRとは会社が持っている資産に対して株価が高く評価されているか否かを示す指標になり、PBRが低いと資産を持っていても株価が評価されていない、つまりお金は持っているのにモテない男性のような状況です。しかし、実際のところ日本企業の半数くらいがPBR1倍割れの状況に陥っているという現状もあり、金融庁もこれを問題視し、1倍割れの是正に乗り出し始めています。



PBRはPERに比べて地味な指標ですが、1倍割れしているかどうかをさっと確認するだけでも企業に対する評価を簡単に読み解けます。


PSR(株価売上高倍率)
最後に少しニッチなPSR(株価売上高倍率)を紹介します。計算式は以下となります。
意味: 売上に対して株価(または企業価値)がどれくらい乗っているか。赤字や利益変動が大きい企業でも、売上成長を評価するために使われます。
IR(Investor Relations)を使い倒す


上場企業は四半期ごと・年度ごとに、決算説明資料や有価証券報告書、中期経営計画などを公開します。実はこれは投資家だけのものではなく、社員にとっても自社理解の教科書です。
- 戦略の方向性:どの事業に資源を配分し、どこで勝ちたいのか。
- KPI:売上、利益、ARPU、継続率、台数、シェア等、何をKPIと認識し重視しているか。
- リスク:為替・原材料・規制・競争など、会社が直面している課題。
「会社が何を目指しているか」「どのように達成しようとしているか」は、IR資料から読み解けます。これらの情報は投資家だけにとって有益な情報ではなく、社員にとっても自社の方向性を再認識することに利用できる有益な情報です。
ざっくり企業の市場評価を読み解く手順(実践)


市場区分を確認
プライム/スタンダード/グロースのどこに上場しているか、そこから企業の属性を推し量る。
時価総額を把握
同業他社と比べて時価総額は大きい?小さい?これまでの推移は?
PER・PBR・PSRをチェック
同業平均と比較してその差に注目する。割高/割安である場合、「なぜなのか」を仮説立てて考える。
IR資料を読み込む
成長投資・コスト構造・一過性要因(特損等)などの詳細を把握するにはIR資料で確認。
まとめ
- 上場は信頼と透明性を前提として資金調達の手段を得る
- 市場区分は企業のステージと投資家の期待を示す
- 時価総額は市場がつけた値札、PER/PBR/PSRをうまく使えば割安/割高を確認できる
- IR資料は投資家だけではなく社員にとっても有益な情報源に
「この会社は市場でどう評価されているのか?」今回紹介した指標や考え方を使って、ぜひ自分なりの仮説を作ってみてください。