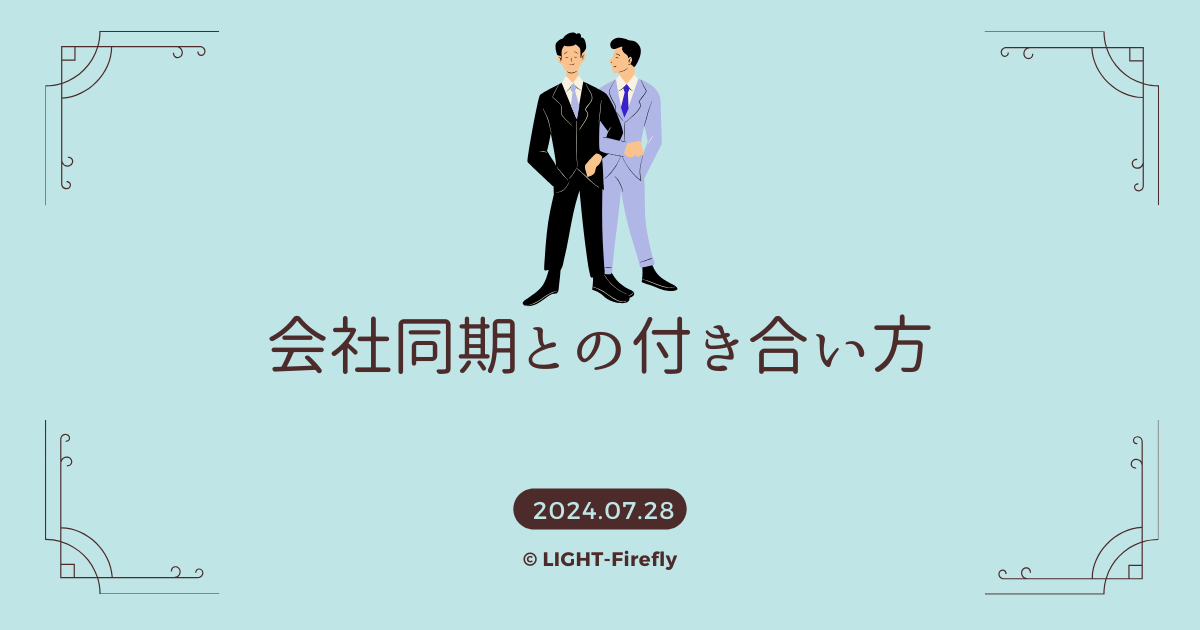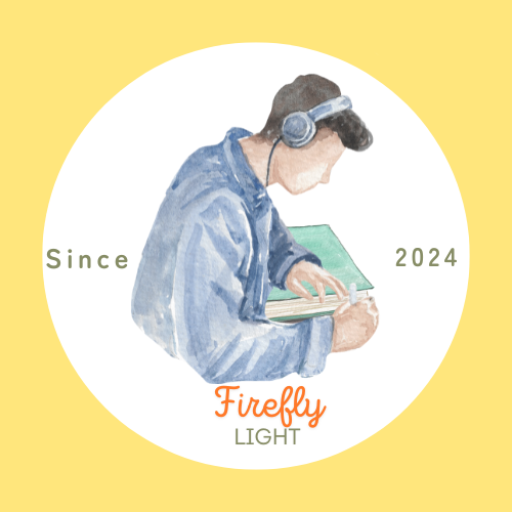
ライト
- 営業経験約10年(主に法人営業)
- これまで中小企業から大企業まで商談経験多数
- 休日はビジネス関連書籍を読み漁み自己研鑽に励む
- 人間関係や仕事の進め方、営業現場での失敗は数知れず
- 当ブログは自身の知識の整理とアウトプットが目的です
当ブログ記事があなたのお役に立ちましたら幸いです!
この記事の読了目安時間は約 2 分です
現代のビジネスにおいて、「商品やサービスのラインナップ戦略」は企業の成功を左右する重要な要素です。そんな中、効果的なマーケティング戦略として注目されているのが行動経済学でも度々紹介される「極端の回避性」です。本記事では、「極端の回避性」をテーマに、商品やサービスを松、竹、梅という3段階のランクに分類する考え方や、その背後にある心理的メカニズム、そして具体的な事例としてNetflixの料金プランやクレジットカードのランク設定を詳しく解説します。
用語解説:行動経済学
出典:共同通信社 共同通信ニュース用語解説
極端の回避性とは
「極端の回避性」とは、消費者や顧客が選択肢の中で極端なもの、すなわち「最上位」または「最下位」を避け、結果的に中間の選択肢(ここでは竹に該当)が選ばれる心理現象を指します。人は本能的に「損失を回避する」傾向を持っており、極端な選択に対してリスクを感じやすくなるためです。
この現象を効果的にビジネスに応用するためには、まず「商品ラインナップを松・竹・梅の3種類に分ける」ことが基本となります。ここでのポイントは、各ランクに明確な役割と価格帯、そして提供する価値を設定することです。たとえば、松ランクは高価格ながらもプレミアムなサービスや付加価値を提供し、梅ランクは手軽に利用できるエントリーレベルの商品とし、竹ランクがその中間に位置するのです。

商品を松竹梅の3ランクに分ける

企業が商品を3つのカテゴリに分けるとき、以下の例を参考に考えることができます。
- 松ランク(プレミアム): 高価格・高付加価値な商品。ここでは、ブランドの信頼性やステータスが重視され、限られた顧客層に向けて強い訴求力を持たせます。経済的に余裕がある層や、特別なサービスに対してプレミアム感を求める顧客にアプローチします。
- 竹ランク(スタンダード): 中間価格で、大多数の顧客が自然と選択するターゲットとなる商品です。ここでは、機能性とコストパフォーマンスのバランスが絶妙に保たれており、「損をしたくない」という心理に働きかける最適解として設計されています。
- 梅ランク(エントリー): 安価でシンプルな商品。初めてそのブランドやサービスを利用する顧客を取り込みやすいエントリーポイントとして機能し、ブランドへの敷居を低くする役割を果たします。
「松:竹:梅」は「2:5:3」の割合で売れる
市場調査や行動心理学の研究によると、消費者は複数の選択肢がある場合、「松:竹:梅」の割合が「2:5:3」で売れると言われています。これは、2割が高級志向の松ランク、3割が低価格志向の梅ランク、そして大多数の5割が、リスクと満足度のバランスが取れた竹ランクを選ぶという現象に基づいています。
この割合は意外に思えるかもしれませんが、その背景には消費者が持つ「損失を回避したい」という強い心理的傾向が大きく影響しています。企業がこの心理を理解し、意図的に商品設計やサービスラインナップに反映させることで、自然な販売促進と顧客満足を同時に実現できます。つまり、竹ランクの商品が企業の売り上げの中心となる戦略が、ビジネスの成功に不可欠です。
売りたい商品を竹にする

多くの企業は、自信を持って販売したい主力商品を中間ランクの「竹」に置くべきです。その理由は、顧客が「竹」を最も安心感を持って選ぶ心理に寄り添うためです。
例えば、もし企業が商品ラインナップを2種類に限定していた場合、顧客は「損をしたくない」という思考から、相対的に安い商品を自動的に選んでしまいます。結果として、お店の売上は思うように伸びず、顧客に対して十分な満足感や価値を提供できない可能性が高まります。ビジネスを戦略的に考えるなら、商品のラインナップは最低でも3種類用意すべきです。
竹ランクに位置付ける商品は、企業が自信を持って推奨できるコア商品となります。 この商品は、利益が十分に取れており、かつ顧客にとってもコストパフォーマンスが高いと感じてもらえることが必要です。実際に、企業が自社の強みや得意分野を再評価し、適切な価格設定と価値提供を行うことで、竹ランクの商品が大多数の顧客に選ばれるようになります。
商品ラインナップは最低でも3種類用意するべきですが、ラインナップが多くなりすぎると消費者が商品を選ぶのを煩わしく感じてしまうリスクが増えます。商品ラインナップを4つ以上に増やす場合は逆に「選び辛くなる可能性がある」というリスクも意識して慎重に考えるべきです。
極端の回避性が使われている例
Netflixの料金プランも松竹梅の設定

実際、世界中で成功を収めるNetflixも、松竹梅の戦略を取り入れています。Netflixの料金プランは、広告付きスタンダードプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランという3段階で構成されています。この設計は、先ほど説明した「極端の回避性」を上手に利用しています。
- 広告付きスタンダードプラン 月額890円(梅ランクに相当):
1080pのフルHD画質で同時に2台まで視聴可能。お手頃な料金でNetflixを楽しめる代わりにほとんどの作品の視聴中に広告が表示されます。 - スタンダードプラン 月額1,590円(竹ランクに相当):
広告なしで映画やドラマが見放題。画質と条件は梅ランクと同等で1080pのフルHD画質で同時に2台まで視聴可能。 - プレミアムプラン 月額2,290円(松ランクに相当):
同時に4台の対応デバイスで視聴が可能。画質もUHD 4KおよびHDR画質で視聴可能になり、最上位プランに位置付けられています。
クレジットカードのランクも3種類
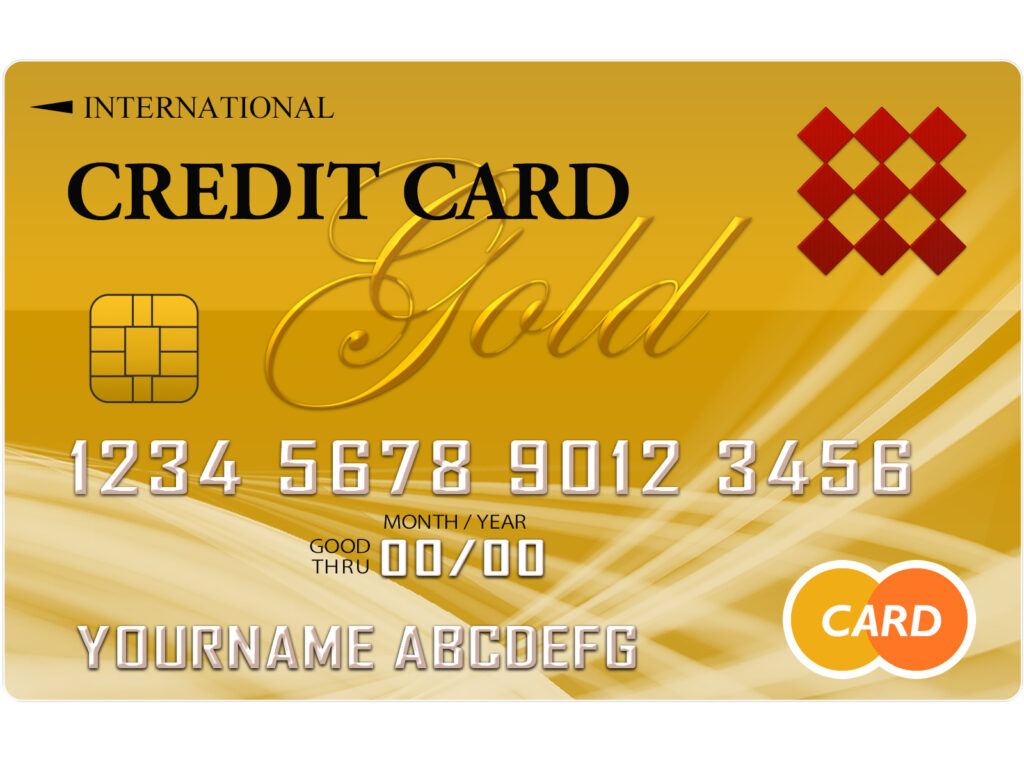
ビジネスにおける商品ラインナップ戦略は、さまざまな業界で応用可能です。クレジットカードの発行もその一例と考えられます。多くのクレジットカード会社は、一般カード、ゴールドカード、プラチナカードという3種類のランクを用意しており、これもまた松竹梅の戦略に基づいています。
クレジットカードはランクが上がるほど年会費も上がりますが、それに伴って特典や優待サービスの内容も充実しています。年会費は無料で基本的な機能を有するエントリーユーザ向けの一般カード、ワンランク上のステータス性や優待サービスを期待する層に向けたプラチナカード、そしてバランスが良く万人にオススメできるゴールドカードというラインナップが基本です。

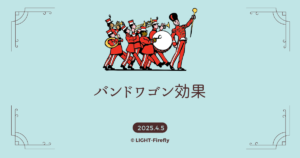

まとめ
本記事では、「極端の回避性」という消費者心理と、松竹梅の3段階商品戦略の有効性について紹介してきました。
- 商品やサービスのラインナップは3種類用意することが大切
消費者は極端な選択肢を避け、中間の「竹ランク」を自然と選ぶ傾向にあります。この現象は、市場における「損失回避」という心理に深く根ざしており、企業側もこれをうまく活用することで、販売戦略の安定化および収益の最大化を図ることができます。 - 「竹ランク」を戦略の中心に据える
売りたい商品やサービスは、自信を持って推奨できる中核商品として竹ランクに位置付けるべきです。これにより、価格と価値のバランスを最も重視する消費者層にしっかりとアプローチすることができ、企業全体の売上向上につながります。 - 成功事例の活用で戦略の正当性を確認する。
Netflixの料金プランやクレジットカードのランク設定は、まさにこの戦略の実例です。どちらも、消費者の選好をうまく把握し、各層に対して最適な価値と価格を設定しています。これらの事例を参考に、自社商品やサービスの設計に応用することが有効です。
企業の成長や市場での競争を勝ち抜くためには、常に顧客の心理や行動パターンに敏感になり、適切な戦略を模索していく姿勢が重要です。「損をしたくない」という消費者の本質的な心理をうまく利用し、松・竹・梅という明快なランク分けを行うことで、新たなビジネスチャンスを創出していきましょう。

飲み物のサイズがS・M・Lの3種類に分けられていたりするのも極端の回避性が使われている例かも。サイズを3つ展開することで「丁度いいサイズ」の提供を実現しているね。